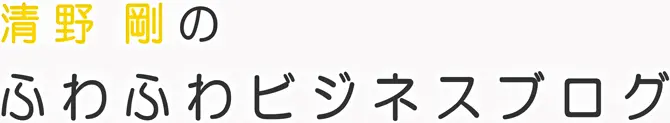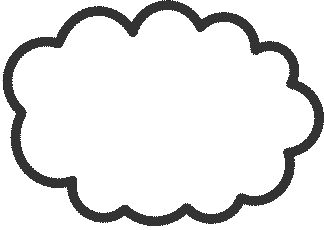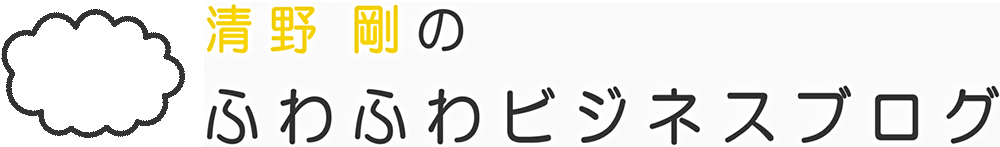米国現地時間7月18日、Metaは次世代のオープンソース大規模言語モデル「Llama 2」の提供開始を発表しました(読み方は「ラマツー」で良いと思います)。満を持して…というよりも、AIビジネスにおける生き残りをかけて…というイメージの方が強い印象です。といいますのも、既に発表と同時にMicrosoftと組むことを発表しているからです。Microsoftといえば、OpenAI社に資本算入しているGPTがありますよね。このLlama 2もGPTやGoogleのPaLM 2と同じLLM(大規模言語モデル)の生成AIであり、そういう意味では競合する事業です。また、Llama 2はWindows搭載を主旨としており、今後はVRやARとLlama 2の連携強化も考えているようで…楽しみなLLMのひとつです。

Llama 2とは
というわけで、Llama 2を軽く紐解いていきます。もともとMetaもAI事業に注力しており、Llama 1は出来上がっていましたが、それをさらに強化したLlama 2ができたとのことです。このLlama 2を普及させるための最大の特徴は、研究利用や商用利用を無償化しているという点にあります。
引用)Metaについてより一部
また、Llama 2はMicrosoft Azureというクラウドサービスを利用して開発する人にとって設計しやすく、Windowsでのローカル動作にも最適化されているとのことです。しかもAWS等のプロバイダとも連携しているので、開発者にとってはこのLlama 2を使って諸々開発するのが楽で積極利用しやすい仕様となっています。
引用)Metaについてより一部
Llama 2ができることは、文章生成やヘルプ、検索エンジン機能、翻訳など、各種生成AIと同じですので、今後Microsoftとの取り組み次第では、GPTではなく、Windowsパソコンに標準搭載されるAIになるかもしれませんね。そうなればGPTはBingとの取り組みに特化していくのかもしれませんが、これは私の100%憶測なので正確な方向性は分かりません。
利用とこれから
すでにこちらのLlama 2サイトから無償でモデルデータのダウンロードが可能で、フォームから、名前とメールアドレス、国名などを入力後、Meta側から送られてくるURLからLlama 2のデータをダウンロードできるという仕組みです。日本語対応はまだまだ弱そうですので、これからに期待って感じかもしれません。
引用)みんなのらくらくマガジン
今後の倫理的な部分に関しては、Metaでは“責任への焦点”と称して、社内外が注力しレッドチーム(安全性のテスト)による演習、モデルのチューニングと評価方法を透明化、責任ガイドやポリシーの作成、Llama 2活用の先駆者向けのコミュニティ、学習チャレンジ・プログラム、学者向けパートナーシップ・プログラム等、あらゆるプロジェクトやドキュメントを策定しています。準備万端って感じですね。
AI市場における普及競争
今回のLlama 2をもってしても、GPTやLamda等の生成AIと明確な機能の違いはありません。精度の違いやビッグデータ処理能力の違いだけが勝負になるでしょう。そうなると、よりビッグデータをインプット、アウトプットできるか、が重要になるわけで、そのためにも普及活動が最重要課題となります。普及されればされるほど、利用者が増え、アウトプットだけでなくインプットが増えます。結果的に開発能力と人材が強化され、勝ち組として加速化するというわけです。
世界的な企業であるGAFAMの中でどれだけ連携できるか、どれだけ先んじれるかが焦点になりますので、私たち利用者側はそれを生温かい目で見守るのみとなっているのでございます(笑)。みんな頑張れー!